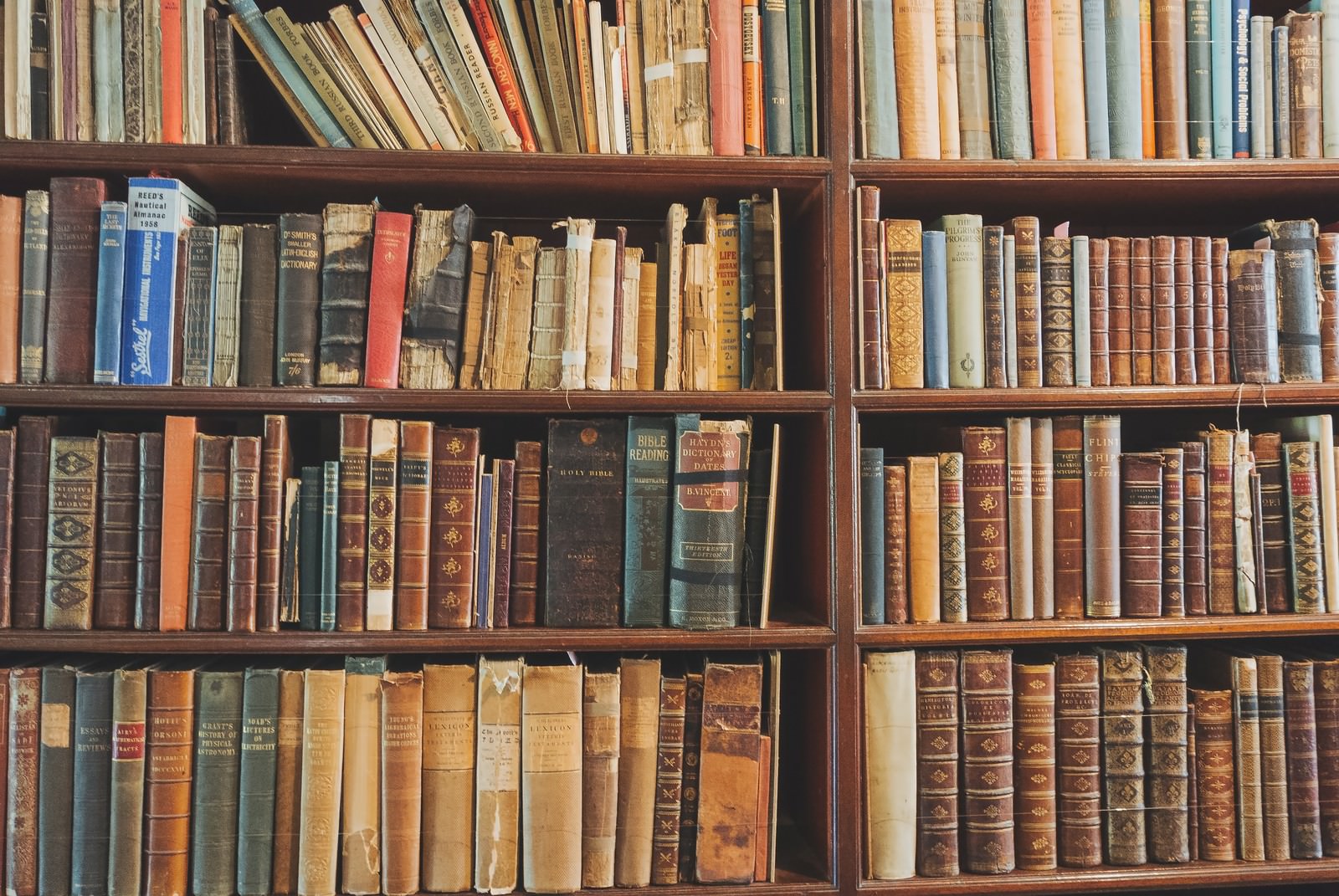ここでは「閑話休題」に似た語を紹介する。
サムネイル:改造社『直木三十五全集 第十四巻』
艶話休題
艶話をやめにする時に用いた語。半村良『亜空間要塞』では「ごそうぞうにまかせて」と読ませた。
けれども是等の貴婦人と稱する多くの婦人の内には同じ令孃姿、同じ奧樣姿で居て、實は別世界に屬する婦人も混入してゐる、艶話休題として
日本商業新報社『日本商業新報 第五五六號』(1915)
甘話休題
スイーツの話題で用いた語。古川緑波の随筆『ロッパの悲食記』の章題として用いられたのが有名。類例では随筆『甘話求題』があり、ここでは「あまいはなし」と読ませている。
甘話休題。この羊羹、砂糖が味覚の表に出ず、あっさりと沈潜し、茶の味と合わさって重厚な品位を示す。
木村栄次『味のパトロール』(1963)
寒話休題
冬の話題で用いた語。汎用性が高くて個人的に好み。
寒話休題。それぢゃ夏はどうかといふと、これがまた霧で一と苦勞することになつてます。
満鐵社員會『協和 270號』(1940)
閑話球題
球技の話題で用いた語。用例多数。国民的スポーツなだけあって、野球の文脈で用いられることが多い。
閑話休題、イヤ・スポーツ漫談だから閑話球題!
吉岡鳥平『筆のホームラン』(1931)
閑話弓題
弓道の話題で用いた語。全日本弓道連盟『月刊 弓道』ではコラム欄のタイトルとして用いられた。
閑話九題
九つの話をする時に用いた語。長崎文献社『長崎おもしろ草 第四巻』で章題として用いられた。「九」の部分は「一」から「十」まで全て用例があり、例えば大野潔『流れがかわった』では幕間のタイトルに「閑話八題」「閑話七題」「閑話四題」と用いた。面白い例では、土方太郎のノンフィクション『閑話九十休題』がある。また、雑誌『労働サロン』の巻頭言を一冊にまとめた『閑話百題』という随筆集もあり、これが最大か。ちなみに内容は百話以上ある。
「閑話休題」と言う語がある。わき道にそれた話を本筋に引き戻す際の常套句だが、この章は本筋を離れたいわば楽屋話だから「閑話一題」と名付ける。
今井正『ドンコの歌』(1985)
閑話Q題
インターネットで用例が散見される語。ブログや動画のタイトル、ハンドルネーム、サークル名などなど。基本的に「Q」に意味はないと思われるが、一部では「QUIZ」「QUESTION」の頭文字として用いているものも見られた。
閑話再開
無駄話を再開する時に用いた語。直前の「閑話休題」と合わせて用いている。
閑話休題。
実力者という連中が決してしないことがひとつある。それは実力者同士がかたまって暮すということだ。本物の実力者はみなバラバラに離れて生活している。集団を作る実力者というのは二流の実力者で、三流以下になるとかたまっていなければ力が出ない。
閑話再開。
半村良『亜空間要塞』(1974)
閑話再休題
無駄話を再びやめにする時に用いた語。「再閑話休題」の例もある。
閑話再休題。私が書こうとしているのはそんなことではなかった。
五木寛之『ゴキブリの歌』(1971)
閑話不休題
無駄話をもう少し続ける時に用いた語。(じゃあわざわざ書くなよ)
閑話不休題。もう一つこの校長の逸話を書きたい。
上田庄三郎『大地に立つ教育』(1938)
漢和休題
日本最大級の漢和辞典『大漢和辞典』の広告のタイトルとして用いられた。「かんわでいっぷく」と読ませていたらしい。
其話休題
それまでの話をやめにする時に用いた語。「それはさておき」とルビを振った例がある。
其話休題として主人はどう惰郎茹り過ぎて仕舞ふぜ
珍聞館『團團珍聞』(1885)
戯話休題
たわごとをやめにする時に用いた語。長与善郎『世相と芸文』に用例がある。
旧話休題
昔話をやめにする時に用いた語。「ふるきはなしはここにとど(めて)」と読ませた例がある。なお、「舊」は「旧」の旧字体である。
舊話休題めて、 此の元祿の末つ方には 江戸の形勢一變して、
塚原渋柿園『大石良雄 前篇』(1906)
喧嘩話休題
喧嘩話をやめにする時に用いた語。「けんかばなしはさておきつ」と読ませた。類例では茶業協会『茶 十一月號』の「喧話休題」があり、そちらは「けんわきゅうだい」と読ませている。
参考文献は『戦後日本ジャズ史』第十四章「国外戦→国内戦・喧嘩論文」をどうぞ。喧嘩話休題――。
清水俊彦、平岡正明、奥成達『日本ジャズ伝』(1977)
私話休題
自分の話をやめにする時に用いた語。「わたくしごとはさておいて」と読ませた。
私話休題(わたくしごとはさておいて、と読んでください)
作家社『作家 No.303』(1974)
這話休題
これまでの話をやめにする時に用いた語。用例多数。「這」は中国語で「これ」という意味を持つ。白話小説でよく見られ、日本でも江戸期より用例がある。『春色袖の梅 十』等では「これはさておき」と読ませた。
這話休題 爰にまた遠江の国 御前崎といふ海岸の山寺に
為永春水『春色袖の梅 十』(1841)
臭話休題
臭いものの話題で用いた語。国立国会図書館では2例確認できるが、どちらも便の話題で用いていた。
笑話休題
笑い話をやめにする時に用いた語。
いつぞやお話した天草版の伊曾保と同様に、この方も探してみたら如何でせう、呵々。笑話休題、古本版の『上野物語』は、私は未だ見たことはありませんが、何處にあるでせうな。
新村出『史伝叢考』(1934)
冗話休題
冗話をやめにする時に用いた語。冗話は冗談、無駄話の意。用例複数。「むだばなしはしばらくおく」と読ませた例もある。
食話休題
食べ物の話題で用いた語。
何故なら、森鷗外の名作『雁』にこの饅頭が出てくるからである......食話休題......さて、甘いものを喰べ、お茶で咽喉をうるおして再びプレーボール。
大和球士『真説日本野球史 明治篇』(1975)
昔話休題
昔話をやめにする時に用いた語。関西空港部会報『新空港レビュー No.100』に現れる。
禅話休題
禅の話題で用いた語。
すなわち茶禅一味ということになるのですが、ここでは禅話休題。
千宗室『一碗のお茶から』(1983)
前話休題
直前の話をやめにする時に用いた語。用例多数。江戸期から用例があり、一部では「前」の異体字の「歬」も用いられた。『貞操婦女八賢誌 四編巻壹』では「はなしふたつにわかる」、『同 七編中』では「そはおきて」、『近世紀聞 十一編巻之三』では「そはさておき」、『忠孝美談』では「それはさておき」、『開山暁幡隆大和上行状略記』では「これよりさき」と読ませるなどルビも多彩である。『開巻驚奇俠客傳 第五集巻之五』では「前話休題却説」で「それはさておき」と読ませた例もある。
前話休題 却説 白虎山の片邊に木澤村といへるあり
杉田伊助『忠孝美談』(1887)
挿話休題
挿話をやめにする時に用いた語。用例複数。実業之世界社『實業之世界 第十三巻 第十九號』では「エピソードはさておき」と読ませた。和洋折衷のルビがオシャレで個人的に好み。また、門脇真枝『安眠法』では「ともかくも」と読ませた。
隅田川乘り切りの先陣、我こそは、と名乘り掛ける敵の無かつたのは残念々々。挿話休題。
実業之世界社『實業之世界 第十三巻 第十九號』(1916)
他話休題
他の語をやめにする時に用いた語。曲亭馬琴『朝夷巡嶋記 第六編 一』では「あだしごとはさておきつ」と読ませた。似た例では「別話休題」がある。
転話休題
話が転換する時に用いた語。井上勤『通俗八十日間世界一周』で用いられ、「はなしかわって」と読ませた。
徒話休題
無駄話をやめにする時に用いた語。「あだしごとはさておき」と読ませた。
シテ見ると矢張り親孝行は少ないかとも存じます、徒話休題まして、
放牛舎一角『名古屋山三郎名誉伝』(1898)
屯話休題
屯話をやめにする時に用いた語。
――たむろ話のひと齣――(中略)閑話でなく屯話休題。
岡橋林氏追懐録編纂委員会『岡橋林氏追懐録』(1964)
秘話休題
秘話をやめにする時に用いた語。近代将棋『近代将棋 20巻 第7号』の「詰将棋秘話」という章題の下で用いられた。
忙話休題
「閑」と「忙」を対比させて用いた語。用例複数。
舞臺の上で、多少の遊びを宥されなければ、淺草の俳優は皆狂人になるであらう。忙話休題(閑話休題ニ非ズ)
アトリヱ社『新版ユーモア小説全集 第五巻』(1939)
傍話休題
わき話をやめにする時に用いた語。曲水社『曲水 第606号』に用例がある。
漫話休題
とりとめのない話をやめにする時に用いた語。『美術日本 文展號』で用いられた。
鰻話休題
鰻の話題で用いた語。
といってもこれは、天然ウナギの場合で、一般市中のウナギ屋のものは、遠州浜松の産、いわゆる養殖物ものだ。鰻話休題。
木村栄次『味のパトロール』(1963)
妄話休題
妄想の話をやめにする時に用いた語。
要話休題
要の話をやめにする時に用いた語。里見弴が「かんじんなことさておき」とルビを振って用いており、その後の文藝春秋『奥野健男作家論集 第2巻』では里見弴の伝記の場面で「かんじんなはなしはさておき」と読ませている。
蜂の巣のなかには女王蜂、働き蜂、......こゝらで要話休題としよう。
里見弴『銀語録』(1938)
与太話休題
与太話をやめにする時に用いた語。改造社『直木三十五全集 第十四巻』で用例があり、「よたわきゅうだい」と読ませている。